【エクスポート・ジャパンの映画ファン発】2025年映画 おすすめランキングベスト10
弊社エクスポート・ジャパン株式会社の映画ファンによる2025年映画TOP10のご紹介です!
M. Yoshihara
2025年12月25日

私が関わっている環境教育NPOでは、中高生の「探究学習」をサポートする機会があります。「探究学習」とは、自ら問いを立て、調べ、考え、そして発表するという、生徒主体の学びのスタイルです。2000年代に「総合的な学習の時間」が学校現場に導入されて以降、特に近年の教育改革を受けて、全国的に広がりを見せています。私自身、長年教育に関わってきた立場として、また中高生の子どもを持つ親としても、この「探究学習」の動きには強い関心を持っています。
今回は、“探究学習の先進校”の一つとされる、都内の私立校・A学園で探究活動の中間報告会が開催されるとのことで、保護者に限らず教育関係者や外部企業の人たちにも広く参加協力の呼びかけがありました。私も自主活動休暇制度を活用し、参加させていただくことにしました。
(※なお、私の子どもが通っている学校ではないため、保護者としての参加ではありません)
A学園では、生徒が1年間を通して探究を行うカリキュラムがあります。今回はそのちょうど折り返し地点として、中間報告会が開催されました。目的は、生徒たちが今取り組んでいる内容や考えたことを共有し、さまざまな立場の大人からフィードバックをもらうことで、今後の探究をより深めていくことにあります。
発表会は前半が中学3年生、後半が高校2年生と、学年ごとに分かれて行われました。
当日は、”生徒たちの発表を傾聴し、フィードバックを行う大人”として、保護者だけでなく、私のような企業・NPOの関係者、そして卒業生など50名以上が参加していました。
私が特に印象的だったのは、発表が始まる前に、学校側から「大人に期待する関わり方」について説明の時間があったことです。どのような視点でフィードバックしてほしいか、どんな声かけが生徒の学びを深めるのか、という点を丁寧に共有してくださいました。
さらに発表後にも、参加した大人の方たち向けの時間が設けられており、先生方や他の方々の感想を聞く場がありました。単に生徒達の発表を聞くだけでなく、関わった大人側にもそれぞれの学びがあったように思います。
発表会では、各教室に「生徒4〜5名+大人2名」という小グループが編成され、生徒たちは順番に自分の探究テーマについてプレゼンを行います。発表のあとには、大人や他の生徒たちからの質問やアドバイスが飛び交うフィードバックタイムが設けられ、それを一人ずつ回していく形で進行していきました。

印象的だったのは、A学園の生徒たちが非常に堂々と発表していたこと。日頃からプレゼンやディスカッションの機会が多いからか、ほとんどの生徒が緊張する様子もなく、自信を持って話し、フィードバックに対しても真剣に耳を傾けていました。
探究のテーマは、生徒の興味関心に基づいて自由に設定できるため、本当に多様です。
たとえば、
分野も、自然科学、文化、ビジネス、産業、スポーツとさまざまで、まさに“混ざり合い”の場になっていました。
探究の進め方も多岐にわたっていて、ネットや文献での調査から始めた生徒もいれば、実際にフィールドワークやインタビュー、アンケートなどに取り組んでいる生徒も。どの方法を選ぶかも、自分たちで考えて決めているようです。
特に印象に残ったのは、生徒たちが “今、悩んでいること”や“行き詰まっている部分”をそのまま共有していたこと。たとえば、
「ここまでは調べてみたけれど、この先どう進めていいかわからない。誰に聞けばいいんだろう?」
「このテーマは面白いと思ったけど、既に情報が出揃っていて、自分が掘ってもあまり新しいことがなさそうだから、ちょっと迷っている」
といったリアルな声が聞こえてきて、「とりあえず調べて終わり」ではなく、行ったり来たりしながら探究しているんだなと感じました。
私が担当したグループでは、「商品券の存在意義」や「日本の米産業」など、大人でも考えさせられるようなテーマが並び、どれも興味深かったです。個人的に注目しているのは、「CO₂排出量を可視化したエコツアーのアプローチ」をテーマに探究を進めている生徒。私が関わっているNPOとも接点を持ちながら、積極的に学びを広げているようでした。
フィードバックの時間には、「面白い視点だね」「私もそれ知りたいって思うよ」といった言葉をしっかりと伝えるよう意識しました。生徒にとって、“親でも先生でもない大人”が自分の探究に関心を持ってくれたという経験は、きっと今後の意欲にもつながるはずです。
さらに、その子が何にワクワクしているのかを一緒に考えながら、時には新しい視点を加えてみたり、行き詰まりへのヒントを一緒に探ってみたり……。そんな風に工夫しながら、フィードバックの時間を過ごしました。
後半は、「発表者とタイトル一覧」が記載された資料が配られ、大人たちがその中から興味のあるテーマを選び、自由に聞きに行く形式でした。各発表には3〜6名程度の大人が集まり、発表後にフィードバックを行います。中には英語で発表している生徒もいました。
資料に目を通してみると、どのテーマも魅力的で、もっとたくさんの発表を聞いてみたいという気持ちになりましたが、残念ながら時間の関係でそれは叶いませんでした。
特に興味を惹かれたテーマは、「日本の城に人を呼び込むにはどうすればよいか」「日本とイギリスの高齢者の違い」「日本のアニメの国際的価値を高めるには」「“大丈夫”という日本語の複雑さ(外国人にどう教えるか)」「多民族共生の秘訣」など。高校生がこうした問いにどう向き合っているのか、もっと聞いてみたかったと感じました。

2026年3月には、探究の成果の最終報告会が開催され、外部の方にも公開される予定だそうです。自分の子どもが通っている学校でなくても、今の中高生がどんなことに関心を持ち、どんな視点で物事を考えているのかに触れられる、大人にとっても貴重な機会になると思います。最近では、A学園に限らず、こうした発表の場を外部に開いている学校も増えてきています。興味のある方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
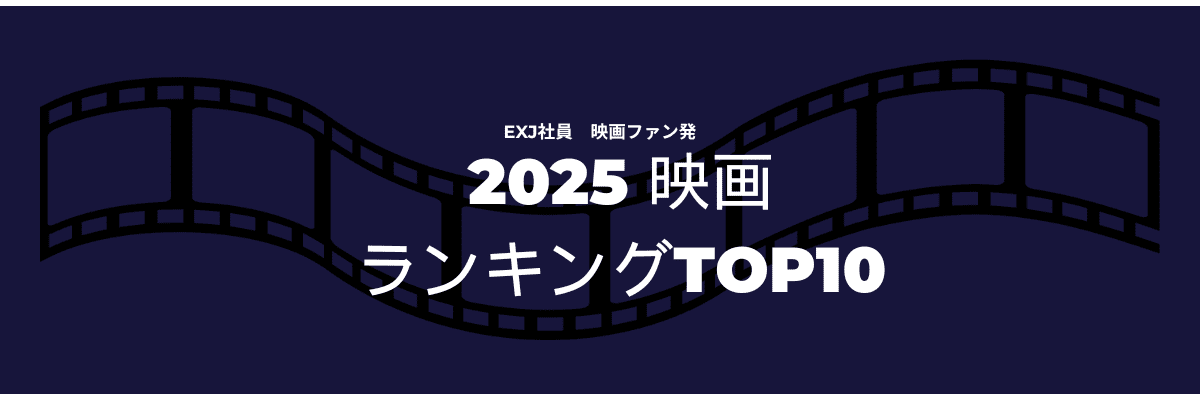
弊社エクスポート・ジャパン株式会社の映画ファンによる2025年映画TOP10のご紹介です!
M. Yoshihara
2025年12月25日

こんにちは!あっという間に秋も深まり、食欲の秋真っ盛りですね。 私たちは、コロナ後からオフィス出社とリモートワークの併用を続けていますが、集まって関係性を深めていく取り組みにも今年は少しずつ取り組んでいます。 今回は、社内のアットホームな雰囲気と、おいしい食べ物、そして社員の笑顔が溢れた...
T. Fukushima
2025年11月21日

2025年10月末、自主活動休暇制度を利用し、自分の誕生日に近い日程で岐阜県の郡上八幡へ旅行に行きました。(紅葉シーズンだと思いましたが、まだ紅葉には早かったです。) 郡上八幡は、名古屋から高速バスを利用すれば、約1.5時間ほどで着きます。仕事とプライベートを合わせて郡上八幡へは全部で5回ほど...
Y. Chen
2025年11月18日